小規模企業共済
まず始めに準備すべきものは小規模企業共済。最大毎月7万円積み立てできる。
個人事業主をやっており20年以上つづけるようであればほぼ間違いなく満額(7万円)まで積み立てをすべきものである。(やらないと損するレベル)
30年間積み立てすれば利回りを含めて3000万円を積み立てることができる。
元本割れする可能性が低く、すべて損金算入(経費化)でき、積み立てた金額に応じて借入もできるため(利率1.5%)、経営状態が悪くなった時にすごく役に立つ。
所得税・住民税・健康保険料(社保・国保)の控除を受けることができる(特に健康保険料の控除がデカイ!)。
受け取り時には退職金控除が使えるメリットも大きい
メリット ・住民税・所得税・健康保険料(国保・社保等)徴収前のお金(経費)を使用できるため節税効果が非常に大きい ・仮に30年間積み立てできたら6000万円程度の退職金を準備できる。 ・共同経営者(妻・夫 等)にも積み立てることができる。例)院長:月額7万円 配偶者(妻・夫)7万円 合計:月額14万円 ・
デメリット ・掛け金納付月数が20年(240か月)未満の任意解約は元本割れする。 ・
国民年金基金
・厚生年金保険加入事業者の場合:確定拠出型年金と合わせて月額2万3000円まで
・厚生年金に入っていない場合 :確定拠出型年金と合わせて月額6万8000円まで
この制度で所得税および住民税の控除(税金を安くすることができる)は受けられるが、健康保険料(社保・国保)の控除は受けられないため小規模企業共済より節税メリットは小さい。
受け取り時には退職金控除が使えるメリットも大きい
確定拠出型年金
前出の国民年金基金とほぼ同じだが、自分で運用商品を選べる点で大きい。
全世界株式・全米株式・先進国株式等の積み立てで、積み立て期間が長い場合には国民年金基金より、利回りが大きくなることも期待できる。
ただし、国民年金基金と同様に節税メリットが小規模企業共済より弱いのでし
倒産防止共済(経営セーフティ共済)
月額20万円、最大800万円まで積み立てすることができる。
小規模企業共済と同様に 所得税・住民税・健康保険料(社保・国保)の控除を受けることができる 。
節税効果は大きいものの、運用利回りがなく、解約時にて退職金控除が受けられないため、全額収入となってしまうため退職金として積み立てるのではなく、廃業時の原状回復工事費用や、所得が少ない、設備投資をする際(設備投資資金なら独立行政法人福祉医療機構や日本政策金融公庫、銀行から借入し設備投資した方が、借入金利を考慮しても借入した方がいいと思う(30万円以上の設備投資すると1年で減価償却されないからね))、に解約して資金確保する等で使用するものである。
取引先の会社が倒産し、資金回収が不可能な場合に運転資金確保のため、積み立て金を元に借入または解約して資金確保する制度であるが、そのような使い方をするものではなく。廃業時のテナント原状回復のための資金に使用されたり、従業員の退職金の支払いのために使用されることが多いと思う。(従業員のための退職金積み立てなら中小企業退職金共済を使用した方がいいと思うが・・・)
メリット
・掛け金は住民税・所得税・健康保険料(国保・社保等)徴収前のお金(経費)を使用できるため節税効果がある
・医院の所得が低い時や解約し、所得が低い時の資金確保ができる
・廃業時に解約し、テナント原状回復費やスタッフの退職金として使用できる。
・
デメリット
・解約返戻金は雑収入として課税されるため、院長本人および専従者に対しての退職金積み立てとしては節税効果が小さい
・掛け金納付期間が12か月以上経過しないと解約金(80%程度)が返戻されない
・掛け金納付期間が40か月以上経過しないと全額返戻されない
・医療法人では加入できない
その他、気を付けること
専従者(家族)に対しては退職金を出すことができない
例えば倒産防止共済で800万円を積み立てしており、廃業時に専従者に退職金として800万円を支給したとしても退職所得にならず一時所得になってしまうため節税メリットがない、
専従者に対して退職所得を得るためには、小規模企業共済や中小企業退職金共済を使用して備えよう。

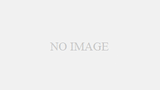
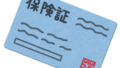
コメント